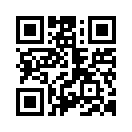2017年05月24日
名称、呼称の持つイメージとその影響
名前とか、呼び名とか、タイトルとか。
それらが持つイメージと、そのイメージが与える影響ってのは、結構デカいよなって思う。
例えば、発達障害などの呼称。
障害の「害」が与えるイメージが誤解を生むという意見もあり、最近は「障がい」と平仮名表記が目立ってきた。
それから、LD、ADHD、自閉症などをまとめて「発達障害」と呼ぶのだが、以前はこれらの総称は「軽度発達障害」と言っていた。
知的な遅れが無いという意味からの「軽度」だったのだろうが、この「軽度」が取り除かれて「発達障害」という言い方になった。
「軽度」=「大したことない」
というイメージで誤解が生じるから、というのがその理由だったように記憶している。
あと、こんな例もあるよね。
「いじめ」という言葉は、その行為の悪質さ、重大さを自覚させることを妨げるんじゃないかという意見。
「いじめ」という言葉で、軽く考えてしまってるんじゃないか、と。
それは「いじめ」ではなく「犯罪」なのだ、と。
「暴走族」って呼称についてもこんな話があった。
暴走族をもっとカッコ悪い呼び方にすれば、やる子も減ってくるんじゃないか、と。
「珍走団」とかね。
これは冗談みたいな話だが、名称、呼称の持つイメージとその影響は馬鹿に出来ないってのは間違いない。
そんな言葉のチカラ、認識した上でつかっていければ良いなー、と思うのであった。
毎日更新される新着情報も要チェック☆
ホクト進学塾のHPへ

Posted by ホクト at 09:15 | Comments(0) | 塾長日記
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。