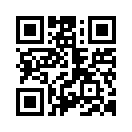2015年10月01日
点数と順位 Part2
はい、前回のおさらいね。『点数と順位 Part1』
小学校の通知表を見ても、「一体これはイイのか悪いのかよくわからない」という感想を持たれる保護者の方は多いのではないかと思う。
唯一、多少なりとも参考になりそうなところと言えば、「よくできる」の数が増えたとか減ったとか、そのくらいだろう。(小学校の先生ゴメンナサイ)
そう、やっぱり分かりやすいのは前回との比較。
中学校に入ると、テストで学年順位が出る。
Part1での内容も踏まえて考えると、順位の「伸び」はどんな学校でも学年でも評価しやすい材料だ。
点数に関して私見を述べると、学校のテストで9割以上の点数が取れたら、無条件に「よくできた」と評価すべきだと思っている。
問題が簡単であろうが何であろうが、そのテストに関してちゃんと出来てるという事は間違いないんだから。
テストの点数、順位、いずれも何を基準に見るか、それをどう捉えるかで、どんな風にも印象は変わってくるものだ。
当然、評価の仕方も様々になる。
最も大切なのは、「次に活かす」ってこと。
そのためにも、指導者にはテスト結果を色んな視点で見る視野の広さが要求される。
パッと見の点数や順位で一喜一憂してる暇は無いのだ。
最後に、ちょっと話が逸れるけど、文科省がやる全国学力調査の結果を自治体が公表するとかしないとかの問題。
あれ、何だか鬼の首取ったみたいに「うちは公表しますよ!」みたいな感じで息巻かれるのも如何なものかと思う。
平均点が全国でどのくらいだとかなんとか、そんなことで教育委員会や世間の目からプレッシャーかけられるのは、現場からすればホント迷惑な話ではないだろうか。
それがために、学力調査が近くなる頃には過去問の演習をやってテスト対策する授業が当たり前になったりしてたら、バカなんじゃないかと思ってしまう。
結果を「次に活かす」ためには、次の「3つの眼」が必要だということで締めたい。
① そこに至る過程を小まめに観察する厳しい眼
② その結果で出た数字を色んな角度から分析する緻密な眼
③ 「まあ、いいじゃん」と結果を大らかに受け止める優しい眼
以上だ。
毎日更新される新着情報も要チェック☆
ホクト進学塾のHPへ